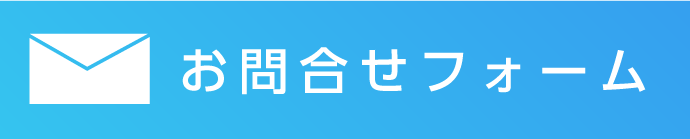地中熱・地下水熱・温泉排湯・空気などの“再生可能エネルギー熱”を熱源としたヒートポンプ製品で「持続可能な社会の実現」を目指します。
2025/1/29
低GWP冷媒対応HPを訴求
パッシブ型ZEBに井水熱源HPを導入
省エネ大賞を共同受賞

低GWP冷媒対応HPを訴求
パッシブ型ZEBに井水熱源HPを導入
省エネ大賞を共同受賞
<記事原稿>
地中熱をはじめとした再生可能エネルギー熱や排熱を熱源とするヒートポンプ(HP)メーカーとして多くの実績を有し、昨年11月に創立40周年を迎えたゼネラルヒートポンプ工業(略称=ZQ。社長=柴芳郎氏、本社・愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14)。同社は「ENEX2025」に出展し、低GWP(地球温暖化係数)冷媒採用の四つのHP(開発中製品含む)を紹介すると共に、再エネ熱や排熱利用HPの様々な導入事例を紹介する。また、同社は2024年度省エネ大賞において、「自然エネルギーを活用したパッシブ型ZEBオフィスの取り組み」で資源エネルギー庁長官賞(ZEB・ZEH分野)を共同受賞しており、ブースではR410Aと、R410A代替の低GWP冷媒であるR454B(A2L<微燃・低毒>、GWP=466)を選択可能な再エネルギー熱対応の水冷HPチラー「ZQS」(ゼットキュースーパー)シリーズを紹介する。R454B採用のZQSは、昨年5月に開庁した福岡県八女市のNearly ZEBの新庁舎で初採用された。その後も北海道の病院や北陸のNearly ZEBのオフィスビル、中国地区の農業施設でも採用されており、その後も受注案件が出てきている。また、低GWP冷媒のR513A(AI<不燃・低毒>、GWP=573を採用した85度Cまでの出湯が可能な産業用プロセスHP「HyPROHP」(ハイプロ)も紹介する。同製品は今年度中に納入見込みの案件があり、その他にも提案中の案件がいくつかある。
空冷の製品だが、再エネ熱を利用できる水冷対応も可能。空調用及び産業用チラーは、フロン排出抑制法に基づく指定製品制度で、2027年度にGWP750の目標値が設定されており、規制に先立って対応を進めている形。これに加え、水冷式ビル用マルチエアコンについても同様の目標が設定されているため、同社はR32採用機種の開発を進めており、近日発売予定。加えて、R407CやR134aを使用しているHPチラー「ZQH」(ゼットキューハイパー)シリーズも、現在開発中のR513Aを採用した低GWPモデルを紹介する。
一方、今回の省エネ大賞の受賞案件は、日建設計、常磐工業、ピーエス、富士エネルギーとの共同受賞。静岡県浜松市のゼネコンである常磐工業が本社ビルを建て替え、自然エネルギーを活用した様々な工夫や設備を導入し、設計値ではNearly ZEBを、運用では一次エネルギー消費量を104パーセント削減して『ZEB』を達成した取組。ここでZQは、負荷の大きいエントランスの冷暖房向けに井水熱源の水冷HPチラーを導入した(二次側はピーエスの除湿型放射冷暖房)。井水蓄熱槽に井水を汲み上げ、冷房負荷が小さい時は井水フリークーリングを行い、負荷が大きい時は追加で井水を熱源とした水冷HPを運転する。また太陽集熱器とそこで得られた温熱の蓄熱槽も設置し、暖房負荷が小さい時はここから温水を送り、負荷が大きい時は追加で井水熱源の水冷HPを運転している。
再エネ・排熱HP様々な事例を紹介
ZQのブースでは、様々な再エネ熱・排熱を利用した水冷式HPの様々な活用事例をポスターで展示する。列挙すると、北海道の「国立アイヌ民族博物館(ウポポイ<民族共生象徴空間>)での地中熱及び地下水利用(2020年竣工)、北海道の蘭越町交流促進センター「幽泉閣」での温泉排湯熱利用(21年設置)、沖縄県の「星の竹富島」での海水熱利用(23年設置)、佐賀県の東よか干潟ビジターセンター「ひがさす」での地中熱利用(20年竣工)、山形県の廃棄物処理場での処理水からの排熱利用(19年竣工)、千葉県の医療法人財団松圓会「東葛クリニック新松戸」での透析廃液からの排熱利用(18年竣工)、富山県の富山市上下水道局での下水熱利用(22年竣工)等。
このうち特筆されるのが、山形県の廃棄物処理での排熱利用の事例だ。廃棄物の最終処分場では、埋立処理施設から毎日240立方メートルもの浸出水(雨水が土壌に染み込まずに浸出水として排出されている)が排出されるため、これを処理して放出している。放水前に生物処理を行うため、以前は、冬期や中間期はボイラで加温していた。だが処理後の放流水は20度C以上もある。そのでこの熱を活用するため、放流水を熱源とするHPを導入。放流水から熱を移動させ、浸出水を加温するシステムを構築した(放流水を溜めておく熱源水槽を構築し、ここに投げ込み式熱交換を投入してHPの熱源としている。加温側にもHP原水槽を構築し、ここに投入した投げ込み式熱交換器で浸出水を処理施設に戻している)。これいによりボイラの稼働を極力抑え、大幅なCO2排出量削減に成功。このシステムは、透析廃液からの熱回収と同様に、同一のシステム内で熱を回収し、熱を使用している。
また、「星のや竹富島」は珍しい海水熱源の事例として特筆される。竹富島では土地を浅く掘るだけで豊富な海水が出てくる。そのでこの事例では井戸を構築し、あらかじめ砂等で濾過された状態の海水を熱源とし、屋外プールの加温に利用している。なお同所では同社の「海水淡水化熱源給湯HP」も稼働している。海水淡水化装置により水資源の乏しい離島でも飲料水を自給すると共に、淡水化した際の温かい水を熱源とする給湯用HPも組み合わせて省エネ給湯を実現。更に太陽光パネルと蓄電池も導入しており、災害時にもシステムの継続運転が可能。
◆
2050年カーボンニュートラルを背景として、同社への引き合いは「増えている感触はある」と柴社長。またZEB案件についても、同社の谷藤浩二常務は「確実に増えている」とし、「以前は当社側でZEBの支援をしていたが、今ではHPを導入した物件が結果的にZEBだったというケースが増えている」と話す。一方で「工場等で排熱利用の引き合いも高まっている」との感触を示し、今回のENEXでは、こうした機運を更に高めたい考えだ。