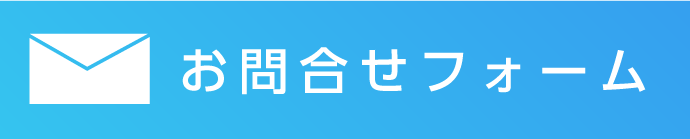地中熱・地下水熱・温泉排湯・空気などの“再生可能エネルギー熱”を熱源としたヒートポンプ製品で「持続可能な社会の実現」を目指します。
2025/4/22
ZEB Orientedの本町サンケイビル、設計者の要望受け
水冷式小型給湯用HPを共同開発
Nearly ZEB 八女市新庁舎では「R454B」ZQSを新採用

<記事原稿>
創立40周年の歴史を有し、地中熱を始めとした再生可能エネルギー熱や、排熱を熱源とするヒートポンプ(HP)メーカーとして数多くの実績を有するゼネラルヒートポンプ工業(略称=ZQ。社長=柴芳郎氏、本社・愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14)。同社には近年、ZEBの依頼が増加しており、以前からの公共案件のみならず民間案件の依頼も増えている。これはZEBの普及が進みつつある状況と共に、同社に対する信頼の高さも物語っている。今回、同社が携わった最近のZEB事例の中から、大阪府の「本町(ほんまち)サンケイビル」と、福岡県の「八女(やめ)市新庁舎」の事例を中心に紹介する。特に前者の案件では、設計者の要望に応えた特注のHPを開発して導入。「これまでに無いものを開発した」(谷藤浩二常務)という点で、同社の小回りの利くHPメーカーとしての強みが如実に表れている。
前者の本町サンケイビルは2021年8月に竣工した超高層ビルで、ZEB Orientedを達成。また、「非接触型」と「喚起」をテーマとして感染症対策にも配慮し、大阪府下で初めて「CASBEE大阪みらいSランク」を取得している。このほど公表された一般社団法人空気調和・衛生工学会の令和6年度表彰では、このビルにおける業績「本町サンケイビルの環境設備計画」が振興賞技術振興賞を受賞。ZQは同賞を、サンケイビル、竹中工務店、伊庭千恵美氏、鈴木修一氏と共同受賞した。ZQの担当は設計・施工・検証。
この案件では、設計を担当した竹中工務店がZEBを達成するため、洗面所の手洗い用の給湯負荷を効率化したいという意向があった。事務所ビルとしての性格上、給湯負荷は小さいものの、一般的に使用される電気温水器は省エネ性が高くないため、ZQに小容量の給湯用HPを作りたいという相談が寄せられた。そこで同社は竹中工務店と共に「水冷式小型給湯用ヒートポンプ」を共同開発した。
同ビルは水冷ビル用マルチエアコンによる水冷熱源空調システムを採用している。熱源は、冷房時は冷却塔をメインに、暖房時は空冷チラーやGHPチラーを運転する。熱源水配管の往管と還管を建物内に通し、この熱源水が各フロアの水冷ユニットに送られ冷媒と熱交換を行う。ここから分流コントローラーを経て各部屋の室内機に冷媒が送られる。各室での冷暖混在運転が可能であり、その際に冷媒配管系統で熱回収運転も可能。
共同開発した水冷式小型給湯用HPは、建物内の熱源水を熱源として、1台で2フロア分の混合栓に温水を循環して手洗い用のお湯を供給する。この建物では7台分のHPを納め、14フロアで給湯を行っている。特筆されるのが熱源水を空調と共有することで、「冷房用の熱源水の温度を下げることができ、結果的に熱回収できること」(同社西日本営業所所長で再生可能エネルギー研究所副主幹の駒庭義人〈こまにわ・よしひと〉氏)。このビルでは冷房の時間が1年間を通しても長いため、長期間にわたる高効率運転にも寄与している。期間平均のシステムCOPは、初年度は2.58で、次年度はチューニングの結果2.66に改善。COPが1以下の電気温水器と比べ、遥かに高効率な値を示した。同社は最近も、負荷に合わせた最適なチューニングを行い、更なる高効率化を目指している。
この事例で開発した水冷式小型給湯用HPはその後、ZQがラインアップに加えて発売した(器機単体のCOPは温水45℃取出しで3.3)。熱源は地中熱等の再エネ熱にも対応する。同製品に対しては、熱回収による省エネなど、同様の発送から具体的な引き合い出てきている。そのほかにも引き合いは寄せられており、「ご興味は持って頂いている」(同)と手応えを示す。
◆
一方、八女市新庁舎の案件は、昨年5月に開庁したNeary ZEBの案件。設計事務所がZEB達成のために地中熱を利用したいという意向があり、同社に相談が寄せられ、同社は設計段階から支援した。熱源機には同社の再エネ熱対応の水冷式HPチラー「ZQS(ゼットキュースーパー)」が採用された。同市庁舎では、熱源井はボアホール深度100メートルを65掘削しており、HPもそれに合わせて5台のモジュールを連結設置した125馬力の大型機を導入。九州では大規模な地中熱利用の事例であり、ベースの空調負荷は地中熱で賄っている。
特筆されるのが、ZQSは冷媒に、R410A代替の低GWP(地球温暖化係数)冷媒であるR454B(A2L〈微燃・低毒〉、GWP=466)が選択できるが、ここでは初めてR454Bが選択されたこと。ZEBを目指すうえでR454B機はR410A機に比べて、環境負荷を低減できることに加えて、COPが高いことも選ばれた要因と考えられる。この案件の後もR454BのZQSは導入実績が出てきている。
◆
このほか、近年同社が携わったZEB案件としては、一昨年12月に竣工した広島銀行の十日市支店・ひろぎん証券三次支店がある。これは109%の『ZEB』を達成しており、地下水を熱源とする水冷チラー、「ZQH(ゼットキューハイパー)が採用された。昨年4月開所した興和の中越支店(新潟県長岡市)では豪雪地帯の中越地方としての初の『ZEB』を達成し、地中熱を熱源とするビル用マルチ「ZP(ゼットピー)」を導入。また昨年9月に竣工したZEB Ready取得の戸田建設の新社屋「TODA BUILDING」でも地中熱熱源の水冷チラーを導入した。
ZEB案件におけるZQの強みの一つは、地中熱をはじめ地下水熱や太陽熱、下水熱等の様々な再エネ熱や、工場排熱を熱源とするHPを展開し、様々な熱源利用のニーズに応えられること。また、同社ではHPの低GWP冷媒化を急務と捉えており、前述のZQSのほか、産業用プロセスHP「HyPROHP」もR513A(A1〈不燃・低毒〉、GWP=573)を採用済み。今後は、指定製品制度において2027年度に規制の始まる水冷ビル用マルチについても「低GWP化の開発を進めている」(谷藤常務)とし、早い段階での発売に向けて準備を整えているとした。